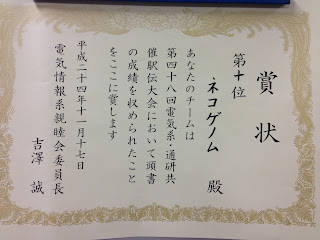担当:齊藤
参加者:9名
節の概要:
基本的には遺伝子発現の過程はどの段階でも調節可能であり、
多くの遺伝子は複数の機構で調節されている。
この節では、RNA合成が始められた後に働く転写後調節について述べられている。
議論した点:
・実際に使うRNAの20倍もRNAを作る意味はあるか?
・RNAの合成にエネルギーを無駄に使っている
・分解等で無駄な労力を使ってしまうのではないか
・RNAの分解にはエネルギーは使わない
・全体で使うエネルギーに対して、RNA合成に使うエネルギーの占める割合が小さいのではないか
・分解されるのはイントロンが多いのではないか
・なぜイントロンはこんなに長い?
・栄養に富むと、イントロンが長くなるのではないか?
・貧栄養状態だとRNAの分解に変化はでるか?
他の議論点:
・転写後の調節はこんなに必要か
・miRNAの塩基対を形成する長さが動物では一般に7塩基対である理由
・RNA干渉の生物学的な意義
・miRNAが調節するmRNAは互いに似ているものか
・RNA干渉で不活性化できないRNAとは?
・3’UTRはなぜ生物種間で保存されていないのか